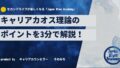はじめに
現代の日本社会では、新型コロナウイルス感染症の影響でデジタル技術の導入が加速するなど、労働市場や働く環境が大きく変化しています。こうした背景を踏まえて策定されたのが、厚生労働省が発表した「第11次職業能力開発基本計画」です。
今回は、この計画の主な方向性やポイントを、具体的な施策と共にわかりやすく解説していきます。
第11次職業能力開発基本計画とは?
「第11次職業能力開発基本計画」は、2021年度から2025年度(令和3年度~令和7年度)までの5年間を対象とした国の職業能力開発の方針を示す計画です。職業能力開発促進法に基づき、働く人々が自律的にキャリアを形成できる環境整備を目的としています。
今後の方向性(4つの柱)
第11次職業能力開発基本計画では、以下の4つの方向性が示されています。
- 産業構造・社会環境の変化を踏まえた職業能力開発の推進
- デジタル化やグローバル化など、社会や産業の変化に対応できるスキルを身につけるための職業訓練を充実させること。
- 労働者の自律的・主体的なキャリア形成の推進
- 働く人一人ひとりが自分自身のキャリアについて主体的に考え、自律的にスキルアップできるようサポートすること。
- 労働市場インフラの強化
- 求職者や企業が必要な情報を効率よく得られるような労働市場の基盤を整備し、マッチング機能を強化すること。
- 全員参加型社会の実現に向けた職業能力開発の推進
- 高齢者や女性、障がい者、非正規労働者など、すべての人が自分らしく働き続けられるよう、職業訓練や能力開発の機会を提供すること。
具体的な施策とわかりやすい解説
1. デジタル技術を活用した能力開発
オンラインでの教育訓練や、ITスキル向上のための講座を充実させ、誰もが気軽に新しい技術を身につけられる環境を整備します。具体的にはAR・VR技術を活用した職業訓練も導入します。
2. リカレント教育(学び直し)の推進
働きながら学べるように、教育訓練休暇制度や短時間勤務制度を推進し、職業人生の節目ごとに必要なスキルを学び直せる環境を整備します。
3. 企業内での能力開発支援
企業が社員のキャリア形成を支援できるよう、キャリア相談制度(セルフ・キャリアドック)の導入や、オンラインで気軽に相談できる環境を作ります。
4. 多様な人材の活躍推進
女性や高齢者、障がい者、非正規雇用労働者など、多様な人材がそれぞれの能力を十分発揮できるよう、個別の特性やニーズに合わせた職業訓練やキャリア支援を推進します。
5. 技能継承と国際協力の促進
熟練技能の継承を促進するとともに、国際的に通用する技能評価システムの普及や技能実習制度の適切な運用を進めます。
6. キャリアプランの明確化支援
不安定な労働市場に対応できるよう、自分自身のキャリアプランをしっかりと立てられる環境整備を行います。
私たちのキャリア形成への影響
この計画の方向性から、私たち働く一人ひとりが主体的に学び、柔軟に変化に対応できる力が求められます。企業側にも、従業員の能力開発を積極的に支援する責任が求められています。企業と個人が共に成長できる環境を目指しています。
まとめ
第11次職業能力開発基本計画は、働き方の多様化やデジタル化、リカレント教育、多様な人材活用などの現代の課題に対応した重要な指針です。私たち自身が自らのキャリアを考え、能力開発に積極的に取り組むことが重要です。
この計画を活用し、自律的で豊かな職業人生を送れるよう取り組んでいきましょう。
(参照:厚生労働省 第11次職業能力開発基本計画)