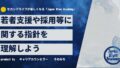はじめに
「残業が多い」「働き方改革」など、働く環境の改善が求められる中で注目されているのが「裁量労働制」や「変形労働時間制」という制度です。しかし、これらの言葉をなんとなく聞いたことはあっても、実際にどのような仕組みなのか、違いがわからないという人も多いのではないでしょうか。
この記事では、裁量労働制と変形労働時間制について、その仕組みやメリット・デメリット、導入時の注意点をわかりやすく解説します。自分の働き方を考えるうえでの参考にしてください。
裁量労働制とは?
裁量労働制の基本
「裁量労働制」とは、実際に働いた時間ではなく、「あらかじめ決めた時間を働いたものとみなす」働き方です。
つまり、何時間働いたかにかかわらず、最初に定めた「みなし労働時間」で労働時間をカウントします。そのため、労働時間の長さではなく、成果を重視した働き方ができるのが特徴です。
対象となる業務
- 企画業務型裁量労働制:企業の事業運営に関する企画・立案・調査・分析を行う業務
- 専門業務型裁量労働制:研究職、デザイナー、弁護士など、厚生労働省が定める専門職種
メリット
- 業務の進め方や時間の使い方に自由度がある
- 労働時間より成果重視の評価が可能
デメリット
- 実際の労働時間が長くなりやすい(自己管理が必要)
- 労働時間の把握が難しく、長時間労働になりがち
変形労働時間制とは?
変形労働時間制の基本
「変形労働時間制」は、1日8時間、週40時間という法定労働時間を、一定の期間の中で調整できる仕組みです。
たとえば、忙しい時期は1日10時間働いて、閑散期には6時間にするなど、月や年単位で労働時間を柔軟に配分できます。
代表的なタイプ
- 1か月単位の変形労働時間制:1か月以内の期間で調整
- 1年単位の変形労働時間制:1年以内で繁忙期・閑散期を調整
- 1週間単位の非定型的変形労働時間制:主にパートタイム労働者向け
メリット
- 繁忙期と閑散期で労働時間を柔軟に配分できる
- 無駄な残業を減らし、生産性向上につながる
デメリット
- 事前にきちんとスケジュールを組む必要がある
- 忙しい時期には長時間労働が発生する可能性がある
裁量労働制と変形労働時間制の違い
| 制度名 | 内容 | 対象 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 裁量労働制 | みなし労働時間制 | 企画業務・専門職など | 労働時間の自由度が高いが、長時間労働に注意 |
| 変形労働時間制 | 時期によって労働時間を調整できる | 一般職・パートタイムなど広範囲 | 繁忙期と閑散期のバランス調整が可能 |
導入時の注意点
裁量労働制の導入時の注意点
- 労使協定の締結や就業規則への明記が必要
- 対象となる業務や職種が限定されている
- 労働時間の実態把握や健康管理措置が求められる
変形労働時間制の導入時の注意点
- 就業規則への記載と労使協定の締結が必要
- 労働時間管理をしっかり行い、過重労働を防ぐ
- スケジュール調整をわかりやすく説明することが重要
まとめ
「裁量労働制」と「変形労働時間制」は、いずれも労働時間を柔軟に設計できる仕組みですが、その目的や適用できる範囲は異なります。
- 裁量労働制は「成果型」の働き方に適し、働く時間の自由度が高い反面、自己管理が求められます。
- 変形労働時間制は「時間調整型」で、業務の繁閑に応じた効率的な働き方が可能です。
制度を正しく理解し、自分や職場に合った働き方を選ぶことが大切です。導入にはルールや手続きが必要なので、職場の労務担当者とも相談しながら活用しましょう。