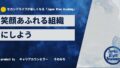就活のエントリーシートもAIにお願いすれば楽勝だ!

その考えは危険かもしれません。理由を解説します。
こんにちは、そのみちです。
人事担当から見る生成系AIを活用したエントリーシートについて
近年、学生の就職活動においてAI技術の進化が大きな変化をもたらしています。特に、米国の新興企業オープンAIが開発した対話型人工知能【ChatGPT】は、エントリーシートの作成や面接対策などに活用され始めています。このような生成系AIを学生がどのように活用できるのか、またその際に注意すべき点について、人事担当者の視点から解説します。
生成系AIの活用例
1. 自己PRの作成
生成系AIを使えば、自己PR文の作成が驚くほど簡単にできます。たとえば、自分の経歴や強みを入力し、「自己PRを300文字で作成してください」と依頼するだけで、AIが的確な文章を作成してくれます。
しかし、そのまま提出するのは避けるべきです。AIが作成した文章はしばしば無個性で、表面的な内容に留まりがちです。そのため、以下の作業を追加することをお勧めします:
- 具体的なエピソードやアピールポイントを追加する
- 不要な要素を削除して簡潔にまとめる
- 自分らしさや熱意を反映させる
2. 面接対策
AIは面接対策にも活用できます。たとえば、エントリーシートをもとに「この内容から面接官が聞きそうな質問を3つ考えてください」とプロンプトを入力すれば、AIが想定質問を提案してくれます。これを活用することで、効果的な練習が可能になります。
ただし、生成された質問はあくまで想定の範囲内です。現実の面接では予想外の質問も出てくる可能性があるため、柔軟に対応できるよう準備しておくことが重要です。
生成系AI活用時の注意点
生成系AIは便利なツールですが、使い方を誤ると逆効果になりかねません。以下のポイントに注意して活用しましょう。
1. 嘘を書かない
AIが提案する魅力的なフレーズやエピソードに引っ張られて、自分を装ったり事実と異なる内容を書くのは厳禁です。嘘は面接で必ず露見します。
2. AI任せにしない
AIが作成した文章をそのまま使うのではなく、自分の言葉で修正することが必要です。AI任せのエントリーシートは、面接時の会話で違和感を生じさせ、選考を通過するのが難しくなります。
3. 自分で理解できる内容にする
AIが提案した文章の中に、自分では理解できない言葉や表現が含まれている場合、それをそのまま使うのは避けましょう。不自然なやりとりになり、面接官に不信感を与える可能性があります。
4. AIの回答を鵜呑みにしない
企業情報についてAIに尋ねることもできますが、その内容が正確である保証はありません。必ず企業の公式サイトや信頼できる情報源で確認しましょう。
5. セキュリティーへの配慮
AIに個人情報や固有名称を入力する際は注意が必要です。入力した情報がAIの学習データとして利用されるリスクを理解したうえで活用しましょう。
人事担当者の本音
エントリーシートは選考過程で重要な役割を果たしますが、最終的には面接の内容が採否の決め手となることが多いです。エントリーシートは面接で掘り下げるための「材料」として利用されるため、AI任せにした無個性なエントリーシートでは、面接官に良い印象を与えることは難しいでしょう。
さらに、生成系AIが作成した文章には熱意や個性が欠ける場合があります。面接官によっては「ChatGPTを活用しましたか?」と直接尋ねられることもあるでしょう。その際、AIをどのように活用したのか、誠実に説明できることが重要です。
エントリーシートは単なる選考突破の手段ではなく、自分を表現し、企業との相性を確認するためのツールです。その本質を理解し、適切に活用することが大切です。
そのみちコメント
生成系AIは社会やビジネスに劇的な変化をもたらしています。それはIT業界も例外ではありません。たとえば、以前はプログラマーとしてプログラムを手作業で組み上げる「職人技」が求められましたが、現在ではプロンプトエンジニアと呼ばれる新しい役割が注目されています。AIを活用し、的確な指示(プロンプト)を出すことで、効率よくプログラムを作成できるスキルが求められる時代です。
50代や60代のエンジニアの中には、これからの技術の進化に不安を抱く方もいるかもしれません。しかし、インターネットが普及した時代やスマートフォンが登場した時と同じように、生成系AIもやがて社会に深く根付いていくでしょう。これからは、AIをどのように使いこなすかが、個人や企業の成長に大きな影響を与える時代になるのです。
まとめ
生成系AIを活用することで、就職活動におけるエントリーシート作成や面接準備が効率化される一方で、AIに依存しすぎると個性や熱意が伝わりにくくなるリスクもあります。
AIはあくまで補助ツールとして利用し、自分らしさを忘れないことが重要です。選考の過程で企業との相性を確認し、自分のキャリア目標と一致するかを見極めながら進めていきましょう。最終的には、ツールの活用よりも「自分をどう表現するか」がカギとなります。