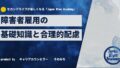はじめに
キャリア支援やカウンセリングの現場で、個別対応と並び注目されている手法が「グループアプローチ」です。これは、複数の参加者が同じ空間や目的を共有し、互いの意見や経験を交換しながら、気づきや学びを得る支援方法です。個人面談だけでは引き出しきれない潜在的な力や、社会的な気づきを促すことができるとして、多くの教育現場や就労支援の場でも活用されています。
本記事では、グループアプローチの基本的な考え方から、キャリア支援の場面における実践的な活用法まで、具体的な例を交えて解説します。
グループアプローチとは?
定義と目的
グループアプローチとは、一定数の参加者が一つのグループとして活動し、相互交流を通じて自己理解や他者理解を深め、目的に向かって成長を目指す手法です。
主な目的
- 自己理解と他者理解の促進
- コミュニケーション能力の向上
- 社会的スキルの強化
- 相互支援・相互啓発の機会の提供
このアプローチは、単なる知識伝達だけでなく「気づきの共有」「感情の受容」など、内面的な成長にもつながる点が特徴です。
活用される場面
1. 学校教育でのキャリア教育
中学生・高校生・大学生などを対象にしたキャリアガイダンスや進路指導の中で、グループディスカッションやロールプレイングを通して将来を考える機会が設けられます。
2. 就労支援現場
ハローワークやジョブカフェ、就労移行支援事業所などで、就活講座やビジネスマナー研修などがグループ形式で実施されています。
3. 企業内研修
新入社員研修やキャリア研修において、チームビルディングやグループワークを通じて職業意識や働く意味を考える機会を提供します。
グループアプローチの種類と手法
オープングループ vs. クローズドグループ
- オープングループ:参加者の入れ替えが自由。ハローワークやセミナーなどで多く活用。
- クローズドグループ:期間とメンバーが固定されており、より深い関係性や自己開示が期待できます。
主な手法
- ワークショップ形式:テーマに基づき、個人ワーク→グループ共有→全体共有の流れ
- ロールプレイ:実際の場面を想定して役割を演じ、対応力を高める
- エンカウンターグループ:自己開示や共感を重視し、心の成長を目指す
- ディスカッション形式:テーマを設け、自由に意見交換する
実践にあたってのポイント
1. 安心・安全の場づくり
グループで自己開示や対話を行うためには、心理的に安全な雰囲気づくりが不可欠です。初回はアイスブレイクを入れ、ルール設定(守秘義務、否定しない、時間厳守など)を明確にしておくことが重要です。
2. ファシリテーターの役割
参加者が自由に発言し、対話を深められるよう中立的に場を導くのがファシリテーターの役割です。参加者の発言を肯定し、必要に応じて問い直しや要約を行うスキルが求められます。
3. 目的とテーマの明確化
ただ集まるだけでなく、「目的」と「ゴール」を明確にすることで、参加者の集中度や満足度が高まります。
活用事例
事例1:大学生向けキャリアワークショップ
将来の進路を考える学生に対し、「10年後の自分を描く」というテーマでグループワークを実施。自分の価値観に気づくとともに、他者との違いから視野が広がったという声が多く聞かれました。
事例2:就労移行支援でのビジネスマナー講座
発達障害を抱える利用者に対して、ロールプレイ形式で面接練習を実施。お互いのフィードバックを通じて、自信や実践力が向上しました。
事例3:企業の中堅社員研修
モチベーションの低下や今後のキャリア不安を抱える中堅社員に対し、同年代の社員同士で「理想の働き方」について話し合うワークを導入。組織の一体感や意欲向上につながる結果となりました。
まとめ
グループアプローチは、単なる情報提供を超えて、参加者同士が“学び合い、気づき合う”貴重な場です。個別支援とは異なり、他者との交流を通じて得られる視点の広がりや内省の深さは、キャリア支援においても大きな効果を発揮します。
効果的に活用するためには、安心できる場づくり、目的の明確化、ファシリテーション技術などが欠かせません。
これからのキャリア支援において、個別対応とグループ対応の“ハイブリッド”での実践が求められていく中、グループアプローチの可能性はますます広がっていくでしょう。
【参考リンク】