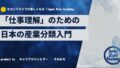はじめに
私たちが日々の生活で目にする「職業」は、実は国によって体系的に整理されています。これは就職活動やキャリア相談、統計の作成など、さまざまな場面で活用されている重要な情報基盤です。
キャリアコンサルタントとして相談に応じる際も、職業分類を理解しておくことで、相談者が知らなかった新たな可能性や選択肢を提案できます。
今回は、日本で使われている職業分類について、基礎から最新の動向まで、やさしく解説します。
日本の職業分類とは?
2つの主な分類
日本には、主に2つの職業分類があります。
-
日本標準職業分類(総務省)
統計調査などに用いられる全国共通の職業分類です。統計の整合性を保つために用いられます。 -
厚生労働省編職業分類(厚生労働省)
ハローワークなど職業紹介の現場で使われる実務的な職業分類です。
階層構造で整理
職業分類は以下のように階層構造で整理されています。
-
大分類:業種ごとの最も大きな分類(例:専門的・技術的職業)
-
中分類:大分類をより細かく分けたカテゴリ(例:医療技術者、教育専門職など)
-
小分類:具体的な職種レベルの分類(例:看護師、小学校教員など)
この構造により、幅広い職業を一貫した基準で扱うことができるのです。
なぜ職業分類が重要なのか?
キャリア支援の基盤
職業分類を理解することで、相談者の経歴や希望にマッチした選択肢を示しやすくなります。分類に基づいて検索や分析がしやすくなり、客観的なキャリア支援が可能になります。
求人・求職の効率化
ハローワークなどで求人・求職を行う際、職業分類番号に基づいて検索が行われています。分類を知っていれば、的確な求人情報にアクセスしやすくなります。
統計調査・政策立案にも活用
職業分類は、労働力調査や就業構造基本調査などで使われ、国の政策づくりや労働市場分析にも貢献しています。
最新の動きと改定ポイント
厚生労働省編職業分類の改定(2022年4月)
-
第5回目の大規模改定が実施されました。
-
AI・IT化の進展や職業実態の変化に対応した分類となっています。
-
たとえば、「情報処理・通信技術者」の中に「AIエンジニア」や「データサイエンティスト」などの職種が追加・整理されました。
ハローワーク職業分類の変更(2023年3月)
-
求人情報システムの職業分類も更新されました。
-
これにより、職業番号やカテゴリが一部変更され、より詳細なマッチングが可能になっています。
まとめ
職業分類は、単なるラベルではありません。キャリア支援、職業選択、統計、求人・求職、すべての基盤となる「共通言語」です。
キャリアコンサルタントとしてこの仕組みを理解しておくことで、より幅広い支援が可能になります。定期的な改定が行われるため、常に最新情報をチェックしておくことも重要です。