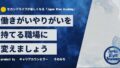内定承諾後に辞退する人が多すぎる。どうにかならないだろうか。

選考の段階ごとに対策が必要です。
こんにちは、そのみちです。
内定承諾後の辞退防止に段階別でやるべき9つの対策
採用予定人数に達し、一安心していませんか?内定が確定した時点でホッとするのは人事担当者として当然のことかもしれません。しかし、内定辞退者が増加している現状を考えると、内定承諾後も入社日までのフォローが非常に重要です。内定をもらった学生が入社に至るまで、適切なサポートを行うことで辞退を防ぎ、入社後の定着にもつながります。
この記事では、内定辞退を防ぐための「採用段階」「内定後」「入社まで」の3つの段階別に具体的な対策を解説します。
採用段階でやるべき3つの対策
1. 自社に適合する人物像を具体的に提示
採用活動の第一歩として、自社が求める人物像を明確にすることが不可欠です。漠然とした表現では、応募者に刺さるメッセージを届けることは難しいでしょう。自社の文化や価値観、仕事の特性に基づいて具体的な人物像を定義し、それを明確に学生に伝えることがポイントです。
2. 詳細で正確な会社情報を提供
学生が会社に不安を抱く理由の一つは、企業の雰囲気や仕事内容が想像しにくいことです。これを解消するためには、先輩社員のインタビュー動画や会社見学会を実施し、リアルな情報を伝える工夫が必要です。学生が会社のイメージを明確に持つことが、安心感につながります。
3. 内定承諾までの十分な考慮期間を設定
内定を出した直後にすぐに返事を求めると、学生はプレッシャーを感じてしまいます。一定の考慮期間を設けることで、学生が慎重に検討し、納得した上で内定を承諾する環境を整えましょう。
内定後にやるべき3つの対策
内定承諾後、入社までの期間には、学生がさまざまな不安を抱きやすい時期です。この期間に適切なフォローを行うことで、辞退リスクを減らし、内定者との信頼関係を深めることができます。
1. 内定者懇親会の実施
内定者同士や職場の社員と直接交流する機会を設けましょう。内定者懇親会や座談会などを通じて、仲間意識を高め、会社への親近感を醸成することができます。
2. 定期的な人事担当者からのフォローアップ
月に1回程度、人事担当者が内定者に連絡を取り、不安や疑問をヒアリングしましょう。短い時間でも内定者の声に耳を傾けることで、心理的な安心感を提供できます。
3. 同期とのコミュニケーション促進
同期となる内定者同士が交流できるオンラインチャットやミーティングを設けることで、横のつながりを強化できます。同期とのつながりがあると、入社後のイメージがより具体的になり、不安を軽減できます。
入社までにやるべき3つの対策
入社までの期間に、内定者が「入社後の働く姿」をイメージできるようサポートすることは、辞退防止だけでなく、入社後の活躍にもつながります。
1. 仕事の意義や会社のビジョンを共有
会社のビジョンや仕事の意義を説明することで、内定者のモチベーションを高めましょう。ただし、不安を煽るような内容は避け、前向きでやりがいのあるメッセージを意識してください。
2. 入社前学習のサポート
入社前に学ぶべき知識やスキルを明示し、内定者が自主的に準備を進められるよう支援しましょう。教材やオンラインリソースを提供することで、具体的な学習プランを提示できます。
3. スキル獲得のための支援
入社前に習得しておくと良いスキルを具体的に伝え、それを学ぶための支援を行いましょう。「何を学べば良いか分からない」という状態を解消するだけでも、内定者の不安を軽減することができます。
そのみちコメント
就職氷河期世代の私は、内定を獲得すること自体が難しい時代を経験しました。当時は内定辞退者は少なく、内定を得ること自体がゴールのように感じられました。しかし、現代では選択肢が多様化し、内定を複数得た上で辞退を考える学生も増えています。
特に「SE(システムエンジニア)」という職種では、仕事内容の幅広さや難しさから、入社後にリアリティショックを受けるケースも少なくありません。入社後のミスマッチが早期退職につながる可能性があるため、採用段階から入社後を見据えた具体的な情報提供が必要です。
会社のリアルな姿や仕事の意義をしっかり伝えることで、内定者が「ここで働きたい」と思える環境を作ることが、内定辞退を防ぐ上で最も重要だと感じます。
まとめ
内定辞退を防ぐためには、「採用段階」「内定後」「入社まで」の各ステップで適切なフォローが欠かせません。具体的な情報提供やコミュニケーションの場を設けることで、内定者が安心して入社できる環境を整えましょう。
採用活動は内定を出した時点で終わるものではありません。内定者が入社後も活躍できるよう、入社までの支援を継続的に行うことが、会社にとっても内定者にとっても最良の結果をもたらします。適切な対策を講じて、内定者との信頼関係を築いていきましょう。