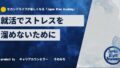テレワークで部下はしっかり仕事ができているだろうか・・・

テレワークでどこまで質問してよいのだろう・・・

立場や役割によって、テレワーク中に感じることは異なります。
こんにちは、そのみちです。
管理職目線と若手社員目線でテレワークの3つ課題
「誰とも話すことなく、一日の仕事が終わった」「成果に対する評価やコメントを直接もらえないので、達成感が薄い」。
テレワークが広がる中で、こうした悩みを抱える人が増えています。
周囲に気軽に質問できる環境がなく、孤独や不安を感じる方も少なくないでしょう。さらに、企業の採用活動でも「御社のテレワーク比率はどのくらいですか?」といった質問が増えており、働き方の柔軟性は企業選びの重要な要素になっています。
では、テレワークの現状と課題について、若手社員と管理職・経営者、それぞれの視点から考えてみましょう。
テレワークの現状
過去の状況(コロナ禍発生直後)
企業
急速にオフィス勤務からテレワークへの移行を余儀なくされました。
社員
感染リスクを避けるためテレワークを希望する人が急増し、通勤時間削減や業務効率化を歓迎する声も多く聞かれました。
学生
就職活動では、テレワークが可能な企業を条件とする学生が増加しました。
現状(2022年10月時点)
企業
働き方の選択肢が多様化し、企業ごとに異なる方針を選択しています。
- オフィス勤務へ回帰
- 完全テレワーク化によるオフィス撤廃
- ハイブリッドワークを採用し、オフィスをコワーキングスペースとして活用
社員
テレワークに慣れた社員と、オフィス勤務を望む社員で二極化が進んでいます。
学生
テレワークを重視する学生と、対面のオフィス勤務を希望する学生が混在しています。
テレワークの3つの課題
テレワークが広がる中で、若手社員と管理職・経営者それぞれに異なる課題が浮かび上がっています。
若手社員の課題
- 孤独感
1人暮らしの若手社員にとって、1日中誰とも話さない環境は孤独感を助長しやすいです。 - オン・オフの切り替えの難しさ
自宅勤務では仕事とプライベートの境界が曖昧になり、リフレッシュするタイミングを失いやすいです。 - 質問しづらい環境
オフィスであればすぐに確認できる些細なことでも、テレワークでは質問が億劫になり、業務が滞るケースがあります。
経営者・管理職の課題
- 部下の状況が見えにくい
部下がどのように仕事を進めているか把握しづらく、適切なサポートが難しくなります。 - 評価の偏り
評価が成果重視に偏りがちで、日々の努力やプロセスを見逃してしまうことがあります。 - 雑談の減少
オフィスでの雑談が減ることで、偶然生まれるアイデアや発想の機会が失われるリスクがあります。
そのみちコメント
コロナ禍でテレワークに移行した当時、私は技術部門の管理職として多くの課題に直面しました。普段、気軽に声をかけたり雑談をしたりすることが減り、部下とのコミュニケーションが希薄になることにストレスを感じました。
SEの仕事では、チーム全体が「一体感」を持つことが不可欠です。しかし、テレワークでは、対面であればすぐに解決できた課題が、オンラインでは時間がかかる場面が多く見られました。テレワークのメリットを感じつつも、オフィス勤務の価値を改めて実感する機会となりました。
ハイブリッドワークが求められる理由
2022年4月以降、対面イベントや歓迎会が再開され、リアルな交流の喜びを再確認した方も多いのではないでしょうか。テレワークによる業務効率化のメリットは確かに大きいですが、それを支える「人と人とのリアルなつながり」もまた重要です。
オフィスでの雑談や対話は、働く楽しさやモチベーションを高め、チーム全体のエンゲージメント向上につながります。一方で、個々の社員が集中して仕事に取り組む環境を提供することも必要です。これらを両立させるハイブリッドワークこそ、これからの企業に求められる働き方の形ではないでしょうか。
結論:柔軟な働き方を追求しよう
テレワークが定着した今、企業としては、テレワークとオフィス勤務を組み合わせた「ハイブリッドワーク」を模索し、柔軟な働き方を提供する必要があります。働き方の多様性を受け入れることは、社会的な課題であると同時に、企業の競争力向上にも直結します。
仕事をするのも人、成果を喜ぶのも人、そしてその喜びを共有するのも人です。柔軟性を持った働き方を実現することで、社員一人ひとりの働きがいやエンゲージメントを高め、企業全体の成長へとつなげていきましょう。